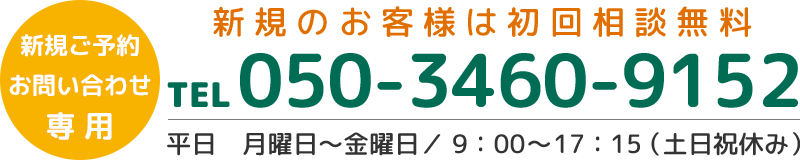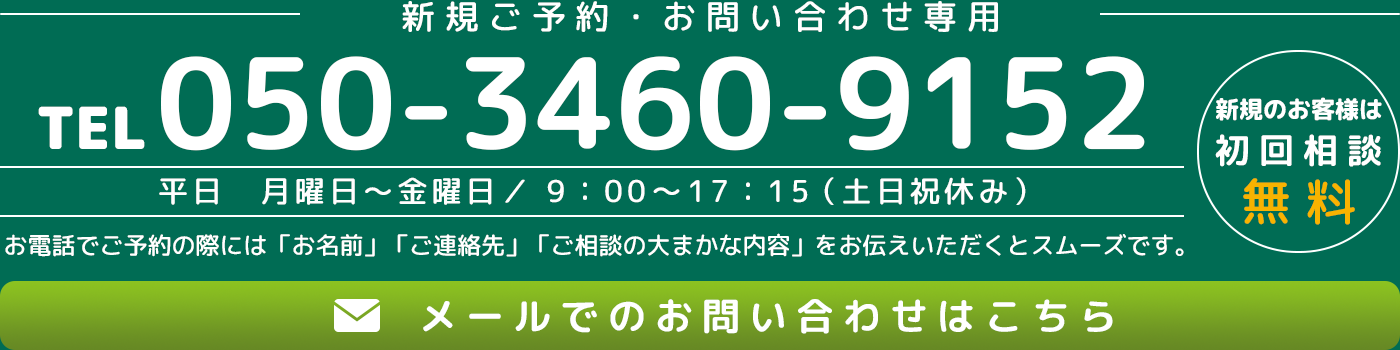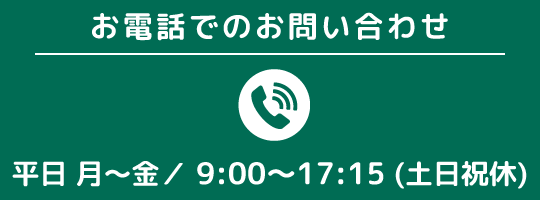Archive for the ‘コラム’ Category
コラム「相続税対策|暦年課税制度と配偶者控除特例を活用した生前贈与の実務ポイント」
1 はじめに|「暦年贈与」と「配偶者控除」を正しく使えば相続税は大きく変わる
相続税対策として、生前贈与を検討される方は非常に多くいらっしゃいます。
なかでも代表的な制度が『暦年課税制度(年間110万円の基礎控除)』と、『贈与税の配偶者控除特例(最大2,000万円)』です。
もっとも、
- 贈与の方法を誤ると思わぬ贈与税・相続税が課税される
- 令和6年以降は生前贈与加算が「7年」に延長され、従来の感覚で対策すると失敗する
といった落とし穴も存在します。
本コラムでは、相続税を合法的に抑えるために知っておくべき暦年課税と配偶者控除特例のポイントを、法令・実務の両面から分かりやすく解説します。
2 暦年課税制度とは|毎年110万円まで非課税となる生前贈与
⑴ 暦年課税制度の基本
暦年課税制度とは、『1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額について、110万円まで非課税(基礎控除)』となる制度です。
この制度を活用し、毎年計画的に贈与を行うことで、
➡ 将来の相続財産を減らし
➡ 結果として相続税の負担を軽減
することが可能です。
⑵ 一般税率と特例税率(直系尊属からの贈与)
暦年贈与の税率には、以下の2種類があります。
- 一般贈与財産:配偶者・兄弟姉妹・子などからの贈与
- 特例贈与財産:直系尊属(父母・祖父母)から、18歳以上の子・孫への贈与
特例贈与財産に該当する場合は、税率が緩和された特例税率が適用されます。
⑶ 暦年贈与の税額計算方法(概要)
贈与税額は、次の計算式で求めます。
贈与税額 =(贈与額 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額
一般贈与財産と特例贈与財産が混在する場合は、法令に基づき按分計算を行う必要があります(措置法・通達)。
👉 税率表の正確な適用や有利不利の判断は専門的判断が不可欠です。
3 【重要】令和6年改正|生前贈与加算が「3年→7年」に延長
令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続税に加算される制度に変更されました。
ただし、
- 延長された4年間分については合計100万円まで非加算
- 贈与の種類によっては加算対象外となる特例も存在
➡ 暦年贈与は「早め」「計画的」がこれまで以上に重要となっています。
4 配偶者控除特例|居住用不動産等の贈与は最大2,000万円まで非課税
⑴ 配偶者控除特例とは
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
- 居住用不動産
- 居住用不動産を取得するための金銭
を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です(相続税法21条の6)。
⑵ 適用要件(チェックポイント)
以下すべてを満たす必要があります。
- 婚姻期間20年以上
- 国内の居住用不動産等であること
- 翌年3月15日までに居住・取得
- 過去に同一配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと
➡ 形式的要件を欠くと特例は適用不可となります。
⑶ 相続開始前7年以内でも「持ち戻し不要」
配偶者控除特例を適用した居住用不動産の贈与は、相続開始前7年以内であっても相続税に加算されません。
そのため、
- 相続税対策
- 配偶者の生活保障
の両面から、非常に有効な生前対策といえます。
5 相続開始年の贈与と「特定贈与財産」
相続開始年に行われた贈与は、原則として相続税の課税対象となります。
しかし、
- 婚姻期間20年以上
- 配偶者控除未使用
- 居住用不動産の贈与
という要件を満たす場合、「特定贈与財産」として生前贈与加算の対象外となります。
👉 相続税申告・贈与税申告の双方が必要となるため、専門家の関与が必須です。
6 遺産分割との関係|配偶者への贈与は「特別受益の持ち戻し免除」が推定
民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与・遺贈は、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。
➡ 相続人間の紛争予防という観点でも重要な制度です。
7 相続税対策は「法務×税務」の同時検討が不可欠
生前贈与や相続税対策は、
- 税務(贈与税・相続税)
- 民法(遺産分割・特別受益)
- 実務(名義・資金管理)
が複雑に絡み合います。
一部だけを見た対策は、後に大きなトラブルを招く可能性があります。
8 【結の杜総合法律事務所の強み】弁護士×税理士によるワンストップ相続対策
結の杜総合法律事務所では、税理士法人を併設し、弁護士・税理士である代表・髙橋が直接対応しております。
- 相続税対策
- 生前贈与の設計
- 遺産分割・遺留分対応
- 相続税申告
まで、一貫したワンストップ対応が可能です。
東北地区では数少ない体制で、実務に即したご提案を行っています。
9 まずは無料相談をご利用ください
制度を正しく使えば、相続税は大きく変わります。
一方で、誤った判断は税務否認・相続トラブルにつながります。
「この贈与は大丈夫?」
「今から何をすべき?」
とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 初回相談無料・無理な勧誘は一切ありません
▶「遺言・相続」ページはこちら
▶「遺言・相続の専門サイト」はこちら
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「【破産・廃業時】未払賃金立替払制度とは?|要件・対象・手続を弁護士が解説」
「会社が倒産して給料や退職金が支払われない」
そのような状況で、労働者を救済する公的制度が未払賃金立替払制度です。
本記事では、法人破産・廃業に直面した場合に問題となる未払賃金立替払制度の仕組み・利用要件・手続の流れを、弁護士がわかりやすく解説します。
未払賃金立替払制度とは【破産・廃業時の従業員救済制度】
未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立替えて支払う制度です。
この制度は、
- 「賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)」
- 労働者健康安全機構
に基づき運用されています。
「解散・清算」と「倒産・廃業」の違いと制度の重要性
解散・清算の場合
会社が解散決議を行い清算する場合は、会社法に基づき官報公告・債権者への催告を行い、原則として公平に債務を弁済します。
倒産・廃業の場合
一方、破産や事実上の倒産では、
- 資産がほとんど残っていない
- 従業員に賃金・退職金を支払えない
というケースが多く、労働者が著しく不利になります。
👉 その救済制度として設けられているのが未払賃金立替払制度です。
対象となる「倒産」の種類【法律上・事実上】
未払賃金立替払制度は、次のいずれにも対応しています。
① 法律上の倒産
裁判所の決定・命令によるもの
- 破産手続開始
- 特別清算開始
- 民事再生手続開始
- 会社更生手続開始
② 事実上の倒産(中小企業)
- 事業活動が停止
- 再開の見込みがない
- 賃金支払能力がない
※労働基準監督署長の「倒産認定」が必要です。
【最新データ】未払賃金立替払制度の利用状況(令和5年度)
- 企業数:2,132件(前年比65.9%増)
- 支給者数:24,300人(前年比71.1%増)
- 立替払額:約86億円(前年比77.5%増)
👉 倒産件数の増加とともに利用が急増している制度です。
未払賃金立替払制度を利用するための要件
① 事業主の要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 労災保険の適用事業所であること
- 1年以上事業活動を行っていたこと
- 法律上または事実上の倒産に該当すること
② 対象となる労働者
- 倒産手続申立日(または認定申請日)の6か月前~2年以内に退職していること
- 労働基準法9条の「労働者」に該当すること
※代表取締役などの役員、同居親族のみの事業などは対象外です。
③ 対象となる未払賃金の範囲と上限額
立替払の対象は、『未払賃金総額の80%(年齢別上限あり)』です。
| 退職時年齢 | 未払賃金総額の上限 | 立替払上限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
| 45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
※賞与・解雇予告手当などは対象外です。
④ 請求できる期間
- 法律上の倒産:裁判所決定日の翌日から2年以内
- 事実上の倒産:倒産認定日の翌日から2年以内
立替払請求の具体的な手続の流れ
【法律上の倒産の場合】
- 破産管財人などから「証明書」を取得
- 必要書類を添付
- 労働者健康安全機構へ提出
【事実上の倒産の場合】
- 労働基準監督署へ倒産認定申請
- 認定後、「確認通知書」を取得
- 必要書類を提出し請求
【重要】会社側(経営者)が注意すべきポイント
- 破産・廃業の判断が遅れると
👉 従業員の立替払利用に影響する場合あり - 書類不備により
👉 支給が遅延・不支給となるケースも多数
👉 法人破産・廃業は、早期に専門家へ相談することが極めて重要です。
法人破産・廃業のご相談は結の杜総合法律事務所へ
結の杜総合法律事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営しており、弁護士・税理士である髙橋が代表を務めています。
- 法人破産・廃業
- 解散・清算
- 未払賃金・従業員対応
- 税務・会計処理まで一括対応
👉 東北でも数少ないワンストップ対応の法律事務所です。
無理な勧誘は一切ありません。
まずは状況整理だけでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
▶ [法人破産のページはこちら]
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「保釈とは?保釈の現状・要件・保証金を弁護士が解説」
Ⅰ 保釈とは何か|刑事事件における重要性
保釈とは、起訴後に勾留されている被告人について、一定の条件のもとで身柄拘束を解き、社会生活を送りながら裁判を受けることを認める制度です。
刑事事件において身体拘束が長期化することは、仕事・家族関係・社会的信用に極めて大きな影響を及ぼします。そのため、
👉 早期に保釈を実現できるかどうかは、刑事弁護における最重要課題の一つ
といえます。
Ⅱ 保釈の現状|日本の保釈率は高いとは言えない
近年、日本における保釈率は緩やかに上昇しています。
- 令和2年度
- 勾留された人員:49,216人
- 保釈された人員:15,431人
- 保釈率:約31.35%
また、平成28年から令和元年までの推移を見ると、
- 平成28年:30.47%
- 平成29年:32.47%
- 平成30年:33.35%
- 令和元年:32.87%
と、30%台を維持しているものの、決して高い水準とは言えません。
保釈率を見る際の注意点
この保釈率には、
- 第1回公判後の保釈
- 結審後、判決前の短期間の保釈
も含まれています。
否認事件や裁判員裁判では、起訴から初公判まで長期間を要することも多く、実質的には長期間身体拘束が続くケースも少なくありません。
だからこそ、
弁護人による早期・的確な保釈活動が極めて重要
となります。
Ⅲ 保釈の要件|いつ・どのように認められるのか
1 保釈は「起訴後」に請求できる(刑訴法88条)
保釈は、起訴された後にはじめて請求可能です。
一般的な流れは次のとおりです。
- 保釈請求書の提出
- 検察官の意見聴取
- 裁判官との面接
- 保釈許可または却下の決定
Ⅳ 権利保釈とは|刑事訴訟法89条
刑事訴訟法89条各号の除外事由がなければ、保釈は「権利」として認められます。
主な除外事由(概要)
- ① 重罪事件(死刑・無期・長期懲役が予定される罪)
- ② 一定の前科がある場合
- ③ 常習性が認められる場合
- ④ 罪証隠滅のおそれ
- ⑤ 被害者・証人への働きかけのおそれ
- ⑥ 逃亡のおそれ
もっとも、これらに形式的に該当しても、直ちに保釈が不可能になるわけではありません。
Ⅴ 裁量保釈とは|平成28年改正で重要性が拡大
裁量保釈(刑訴法90条)
権利保釈の除外事由がある場合でも、
裁判所が「適当」と判断すれば、職権で保釈を許可できます。
平成28年の法改正により、裁判所が考慮すべき事情が明確化されました。
裁判所が考慮する主な事情
- 逃亡・罪証隠滅のおそれの程度
- 身体拘束が続くことによる
- 健康上の不利益
- 経済的影響
- 社会生活への支障
- 防御権行使への影響
裁量保釈を実現するために重要な主張例
- 捜査がほぼ終了していること
- 関係者との接触のおそれがないこと
- 示談成立や被害回復の状況
- 家族・雇用主などの身元引受人の存在
- 定職・住居が安定していること
- 偶発的犯行で再犯のおそれが低いこと
👉 具体的な事実・資料を示して説得的に主張できるかが、結果を大きく左右します。
Ⅵ 保釈保証金はいくらか|相場と減額の可能性
一般的な相場
- 約150万円~300万円程度
ただし、刑事訴訟法93条2項により、
- 犯罪の性質・内容
- 被告人の資産・収入
- 性格・生活状況
などを考慮し、「相当な金額」でなければならないとされています。
そのため、
- 資力が乏しい
- 逃亡のおそれが低い
といった事情を丁寧に主張・立証すれば、
👉 150万円未満となるケースも実際に存在します。
Ⅶ 保釈が却下された場合の対応
保釈が却下されても、
- 準抗告
- 抗告
- 再度の保釈請求
など、引き続き身体解放を目指す手段は残されています。
あきらめず、状況の変化や追加資料を踏まえて再チャレンジすることが重要です。
Ⅷ 弁護士に早期相談する重要性
保釈は、
- 弁護士の経験・判断力・主張の組み立て方
- 裁判官・検察官への説明力
によって、結果が大きく左右されます。
特に、
「起訴直後の初回保釈請求」
が極めて重要です。
Ⅸ 最後に|刑事事件・保釈のご相談はお早めに
保釈は、被告人本人だけでなく、
ご家族の生活・将来を守るためにも極めて重要な制度です。
結の杜総合法律事務所では、
- 刑事事件の今後の見通し
- 保釈の可能性
- 費用・手続の流れ
について、弁護士が直接・丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘は一切ありません。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「破産するおそれのある会社から事業譲渡を受ける際のリスクとは― 倒産前M&A・事業譲受で必ず押さえるべき法的注意点 ―」
1 はじめに|「安く買える事業」には落とし穴がある
物価高や景気低迷が続く中、資金繰りに苦しむ企業が事業の一部を譲渡するケースは年々増えています。
一方で、譲受側から見れば、
- 「有望な事業を安価に取得できるのではないか」
- 「同業他社の顧客・ノウハウを引き継げるのではないか」
と考え、前向きに検討されることも少なくありません。
しかし、譲渡元の会社が破産に近い状態にある場合、
事業譲渡そのものが後から覆される、極めて重大なリスクが潜んでいます。
本コラムでは、
破産するおそれのある会社から事業譲渡を受ける際に問題となる主な法的リスクと注意点を、実務・裁判例を踏まえて解説します。
2 破産管財人による「否認権」とは|事業譲渡が無効になるリスク
(1)否認権の概要
譲渡会社が破産した場合、
破産管財人は、破産手続開始前に行われた一定の取引を「否認」する権限を有します(破産法160条以下)。
事業譲渡が否認されると、
- 譲り受けた事業・資産の返還
- 返還できない場合は金銭による価額償還
を求められる可能性があります。
つまり、正規の手続きを踏んで契約したとしても、安全とは限らないのです。
(2)事業譲渡で問題となりやすい否認類型
事業譲渡との関係で、特に問題となるのは以下の類型です。
① 詐害行為否認(破産法160条1項1号・2号)
- 破産者が債権者を害することを知りながら行った行為
- 支払停止後などに行われ、債権者に不利益を与える行為
👉 譲受会社が「資金繰り悪化」や「破産の危険」を知っていた場合、否認される可能性が高まります。
② 無償否認(破産法160条3項)
- 無償、または無償と同視できるほど不当に低廉な価格での譲渡
👉 「格安での事業譲受」は、極めて危険です。
(3)裁判例から見る否認リスク
裁判例では、
- 実質的に無償で取引先関係を移転させた事案につき無償否認を認めた例
- 事業譲渡について詐害行為否認を認め、価額償還を命じた例
など、譲受会社に厳しい判断が数多く示されています。
3 破産していなくても要注意|債権者の「詐害行為取消権」
(1)民法上の詐害行為取消権
譲渡会社がまだ破産していない場合でも、
債権者は民法424条以下に基づき、事業譲渡の取消しを求めることができます。
- 債務者が債権者を害することを知ってした行為
- 譲受人も害意を知っていた場合
には、取消しが認められる可能性があります。
(2)期間制限にも注意
- 債権者が事実を知ってから2年
- 行為時から10年
を経過すると行使できなくなりますが、
取引後、長期間リスクが残る点は看過できません。
4 商号続用による責任|社名を引き継ぐリスク
事業譲受後、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、
譲受会社が譲渡会社の債務についても責任を負う可能性があります(会社法22条)。
- Webサイト
- 商品パッケージ
- 名刺・看板
などの扱いには、特に注意が必要です。
5 詐害的事業譲渡における譲受会社の責任(会社法23条の2)
譲渡会社が、
- 債権者を害することを知りながら事業譲渡を行った場合
には、
譲受会社は、承継した財産の価額を限度として責任を負う可能性があります。
もっとも、破産・再生等の法的倒産手続が開始されている場合には、
この責任が否定されるケースもあり、事案ごとの精緻な判断が不可欠です。
6 まとめ|倒産前事業譲渡は「専門家関与」が不可欠
破産するおそれのある会社からの事業譲受は、
- 否認権
- 詐害行為取消権
- 商号続用責任
- 譲受会社の直接責任
といった複数の重大リスクを伴います。
特に、
- 不当に安い価格
- 無償に近い譲渡
- 譲渡会社の資金繰り悪化を認識している場合
には、後日、事業を失う可能性すらあることを十分理解しておく必要があります。
【経営者の皆様へ】事業譲渡・M&Aは事前相談が重要です
結の杜総合法律事務所では、
- 事業譲渡・M&Aにおける法的リスク分析
- 倒産・破産を見据えた事業再編の助言
- 税理士事務所併設による税務面を含めたワンストップ対応
を行っております。
「この事業譲渡は安全なのか?」
「後から責任を追及されることはないか?」
とお悩みの方は、契約前に必ずご相談ください。
無理な勧誘は一切ございません。
👉 まずはお気軽にお問い合わせください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「遺留分侵害額の算定方法とは?― 生前贈与・遺言がある場合の具体的な計算と注意点を弁護士が解説 ―」
1 はじめに|「全財産を長男に」という遺言でも、何ももらえないとは限りません
相続において、次のようなご相談は非常に多く寄せられます。
Q
「夫が『全財産を長男に相続させる』という遺言を残して亡くなりました。
相続人である私や二男には、何か請求できる権利はあるのでしょうか。
また、遺留分侵害額はどのように算定するのですか。」
A
遺言によって相続分が指定されていても、一定の相続人には「遺留分」が保障されています。
遺留分侵害額は、
①相続開始時の財産+②一定期間内の生前贈与-③債務
によって算定され、その金額に法定相続分と遺留分割合を乗じて計算します。
本コラムでは、遺留分侵害額の具体的な算定方法について、条文・判例を踏まえながら、実務上問題となりやすいポイントを中心にわかりやすく解説します。
2 遺留分侵害額の基本的な計算式
遺留分を算定するための財産の価額は、次の式で計算します(民法1043条1項)。
遺留分算定の基礎財産
=
① 相続開始時に被相続人が有していた積極財産
+
② 遺留分算定の対象となる生前贈与
-
③ 被相続人の債務(借金・未払金など)
この金額に、
- 各相続人の法定相続分
- 各相続人の遺留分割合
を掛け合わせた額が、具体的な遺留分額となります。
相続や遺言によって取得した財産がこの金額に満たない場合、不足分について遺留分侵害額請求を行うことができます。
※遺留分侵害額の算定時点は相続開始時であり、相続開始後に誰かが債務を弁済していても、原則として算定に影響はありません(最判平成8年11月26日)。
3 「相続開始時に有していた財産」とは何か
ここでいう「財産」とは、被相続人の積極財産を指します。
(1)算入されるもの
- 不動産
- 預貯金
- 株式・投資信託
- 売掛金・貸付金 など
(2)算入されないもの
- 祭祀財産(仏壇・位牌・墓地等)(民法896条・897条)
(3)評価が難しい財産がある場合
条件付き権利や評価困難な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって価格を定めます(民法1043条2項)。
4 生前贈与はどこまで遺留分算定に含まれるのか
生前贈与を自由に認めてしまうと、遺留分制度が形骸化します。一方で、すべてを遡及すると取引の安全が害されます。
そのため、民法は次のようなルールを定めています(民法1044条)。
(1)原則
- 相続開始前1年以内の贈与
→ 原則としてすべて算入 - 1年以上前の贈与
→ 贈与者・受贈者双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」のみ算入
(2)相続人への贈与の特則
相続人に対する贈与については、
相続開始前10年間にされた「特別受益」に該当する贈与が算入対象となります(民法1044条3項)。
(3)贈与と同視される行為
- 無償の信託利益の供与
- 共有持分の放棄
- 寄附行為 なども、贈与と同様に扱われます。
5 不相当な対価での売買(実質的な贈与)
時価とかけ離れた価格で行われた有償行為については、
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り、
贈与とみなされ、遺留分算定の対象となります(民法1045条2項)。
6 贈与の評価時点はいつか
- 相続開始前1年以内の贈与
→ 贈与契約時を基準(通説・裁判例) - 金銭贈与
→ 相続開始時の貨幣価値に換算して評価(最判昭和51年3月18日)
7 控除される「債務」の範囲
遺留分算定において控除される債務には、以下が含まれます。
(1)含まれるもの
- 借金・未払金
- 租税・公租公課
- 罰金などの公法上の債務
(2)含まれないもの
- 相続税
- 遺産管理費用
- 遺言書検認申立費用 など
相続人自身が被相続人に対して有していた債権・債務についても、混同による消滅を前提とせず、相続開始時の客観的財産状態を基準に判断されます(さいたま地裁平成21年5月15日判決)。
8 「全財産を一人に相続させる」遺言がある場合の算定
相続人の一人に全財産を相続させる遺言がある場合でも、他の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
この点につき、最高裁平成21年3月24日判決は、
相続債務も含めて指定相続人が承継するのが原則としたうえで、
遺留分侵害額の算定において、
遺留分権利者の法定相続分に相当する債務額を加算することはできない
と明確に判断しています。
9 「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは?
贈与当事者に悪意や害意まで必要ではありませんが、
- 贈与財産が残存財産を上回ること
- 将来、財産状況に大きな変動がないこと
などを具体的に認識していたことが必要とされています(大判昭和11年6月17日)。
10 まとめ|遺留分侵害額の算定は専門的判断が不可欠です
遺留分侵害額の算定は、
- 生前贈与の有無・時期
- 不動産や株式の評価
- 債務の取扱い
- 遺言の内容
など、高度な法的判断と実務経験が不可欠です。
少しの評価の違いで、請求できる金額が大きく変わることも珍しくありません。
11 弁護士への相談のご案内
結の杜総合法律事務所では、
- 遺留分侵害額請求が可能かどうか
- おおよその請求額の見通し
- 手続の流れ・期間・費用
について、弁護士が直接、丁寧にご説明しております。
無理な勧誘は一切ありません。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「交通事故における損益相殺とは?|示談金が減額される仕組みを弁護士が徹底解説」
1 はじめに
交通事故の被害者が、治療費や休業損害などとは別に、労災保険・自賠責保険金・各種社会保険から給付を受けた場合、それらが損害賠償から差し引かれるのか——。
示談交渉の現場では、ほぼ必ず問題となる重要な論点です。
本コラムでは、交通事故の損害賠償で必ず押さえておくべき 「損益相殺」 について、裁判例をふまえてわかりやすく解説します。
2 損益相殺とは?(基本概念)
損益相殺とは、交通事故などの不法行為による損害賠償額を算定する際に、
事故を原因として損害だけでなく利益も受けた場合、その利益を損害額から控除し、公平な負担を図る考え方
をいいます。
法律上の明文規定はありませんが、
「損害の公平な分担」(民法709条の趣旨)に基づく重要な法理として確立しています。
3 交通事故で損益相殺の対象となる主なもの(実務でよく問題になる給付)
損益相殺の対象になるかどうかは、
- 給付の目的・趣旨
- 加入費用の負担者
- 加害者に対する代位取得の有無
などを総合的に考慮して判断されます。
① 自賠責保険金
自賠責保険は被害者救済を目的とした制度で、支払われる保険金は損益相殺の対象とされます(最判昭39・5・12)。
政府保障事業の填補金も同様です。
② 労災保険の給付金
労災保険給付は損害を填補する性質を持ち、代位取得の規定(労災12の4)もあることから、損益相殺の対象です(最判平8・2・23)。
ただし、
- 休業特別支給金
- 障害特別支給金
などの「特別支給金」は損害補填が目的ではないため、損益相殺の対象外とされています。
③ 各種社会保険の給付(健康保険・厚生年金・共済など)
損害と同質性が認められる場合、損益相殺の対象となります。
例:
- 障害厚生年金(最判平11・10・22)
- 遺族厚生年金(最判平16・12・20)
- 障害基礎年金(最判平11・10・22)
- 健康保険の傷病手当金・高額療養費 など
④ 人身傷害補償保険金
実損填補型であり、代位規定も存在するため、損益相殺の対象です(最判平20・10・7)。
ただし、控除される金額は「自己過失分を超えた部分」に限定されます。
4 損益相殺ができる範囲(費目ごとの制約)
損益相殺は、同じ損害項目間でのみ行われるという重要な原則があります。
例えば、
- 労災の休業補償給付 → 休業損害(逸失利益)から控除
- 慰謝料から控除することは不可(最判昭58・4・19)
- 積極損害から控除することも不可(最判昭62・7・10)
どの費目からどこまで控除されるかは、示談交渉・裁判でも頻繁に争点になります。
5 損益相殺ができる範囲(将来給付の扱い・時的制約)
年金給付や将来の介護給付など、将来の給付が確定していないものは原則として損益相殺の対象となりません(最判平5・3・24)。
理由:
- 将来の給付は不確実性がある
- 債権取得のみでは現実の補填とはいえない
ただし、政府保障事業との関係では特則があり、
将来受給予定分も含めて控除されるという裁判例があります(最判平21・12・17)。
6 生命保険は損益相殺の対象になるか?(結論:ならない)
生命保険金は、
- 契約者が支払った保険料の対価
- 事故と無関係に支払われるもの
であることから、損益相殺の対象外です(最判昭39・9・25)。
傷害保険などの定額給付型保険も同様です。
7 搭乗者傷害保険金は損益相殺の対象か?(対象外)
搭乗者傷害保険は、
- 加害者に代位取得しない
- 損害補填ではなく搭乗者保護が目的
であるため、損益相殺の対象外とされています(最判平7・1・30)。
8 自損事故保険金も損益相殺の対象外
自損事故保険金も生命保険に近い性質を持ち、定額給付・代位なしのため、損益相殺の対象外と判断されています(東京高判昭59・5・31)。
9 まとめ:損益相殺は極めて複雑。示談前に弁護士へ相談すべき理由
損益相殺は、
- 何が控除されるか
- どこから控除されるか
- 控除できる時点
など、裁判例が多数存在し非常に複雑です。
保険会社が最初に提示する金額は、裁判で認められる金額より低いことが一般的です。
一度示談書にサインしてしまうとやり直しはできません。
そのため、示談提案があった場合は、必ず弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。
結の杜総合法律事務所へのご相談について
当事務所では、交通事故に関する損害賠償・示談交渉・後遺障害申請などについて、
弁護士が直接、今後の流れや費用を丁寧にご説明します。
無理な勧誘は一切ありません。
弁護士費用特約があれば、相談料・弁護士費用の自己負担は原則ゼロ
まずは保険証券をご確認いただくか、保険会社へお問い合わせください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「離婚原因と離婚が認められる基準(許否基準)をわかりやすく解説」
1 はじめに|不貞をした夫から離婚請求された…応じる必要はある?
ご相談例
「夫は、私の暴言に耐えられないと言って突然家を出ましたが、実際には女性と同棲するためだったことが判明しました。私は不貞をした夫から離婚を求められる理由はないと思いますし、応じる気持ちもありません。このような場合でも離婚しなければならないのでしょうか。」
回答のポイント(結論)
・協議離婚や調停で話し合いが整わない場合、離婚訴訟に進みます。
・裁判所が離婚を認めるのは、「民法770条の離婚原因」がある場合に限られます。
・不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、一定の条件を満たさなければ認められないことがあります。
離婚原因の有無、有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかが大きなポイントになります。
2 離婚までの手続の流れ|協議→調停→(審判)→訴訟
夫婦の離婚方法は次の4つです。
- 協議離婚(民763)
- 調停離婚(家事244・268①)
- 審判離婚(家事284①〜③)
- 裁判上の離婚(民770)
協議でまとまらなければ、基本的には、家庭裁判所の調停 → 訴訟の順で進みます(審判離婚は比較的少数)。
3 離婚原因とは|民法770条の5つの類型
(1)離婚の訴えができるケース
民法770条1項で定める離婚原因は次の5つです。
- 不貞行為(配偶者以外との性的関係)
- 悪意の遺棄(正当理由なく同居・扶助義務を放棄)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病で回復の見込みがないもの
- 婚姻を継続し難い重大な事由
①〜④は「具体的離婚原因」、⑤は「抽象的離婚原因」と呼ばれます。
また、①②は有責的離婚原因、③④は非有責的離婚原因、⑤はいずれも該当し得ます。
裁判所は、①〜④の事由があっても、夫婦関係の全事情を考慮し「婚姻を継続すべき相当性」があれば離婚を認めないことがあります(770条2項)。
(2)不貞行為
・自由意思に基づき配偶者以外と性的関係を結ぶこと。
・性的行為類似行為も、夫婦共同生活の平和を侵害する程度によって不貞と評価されることがある(東京地判令3・2・16)。
・同性間の性的行為も「婚姻を継続し難い重大な事由」とされた例があります。
(3)悪意の遺棄
正当な理由なく同居・協力・扶助義務(民752)に反すること。
やむを得ない事情がある場合は悪意の遺棄とは言えません。
(4)3年以上の生死不明
「最後に生存が確認できた時点」から起算します。
(5)強度の精神病
・婚姻生活が維持できないほどの精神疾患
・長期間の治療でも回復のめどが立たないこと
・療養環境の確保が図られているかにより判断が変わる(最判昭33・7・25、昭45・11・24)
(6)婚姻を継続し難い重大な事由の具体例
代表的なもの(裁判例ベース):
- 暴行・虐待
- 暴言・侮辱
- 家庭の放置
- 働く意欲の欠如
- 過度の浪費・借金
- 飲酒・薬物問題
- 背信行為
- 長期間の別居
- 親族との不和
- 訴訟・告訴
- 過度な宗教活動
- 同性愛
- 性生活の異常
- 病気・障害
- 性格の不一致・価値観の相違
- 愛情の喪失 ほか
特に「長期別居」(例:4年10か月で破綻と判断した例あり)は、重要な判断材料となりますが、
別居7年でも「破綻といえない」とされた例もあり、事情次第で結論が変わります。
離婚原因の有無は、客観的な事実を丁寧に主張・立証できるかが極めて重要です。
4 有責配偶者からの離婚請求|不貞をした側でも離婚できるのか?
従来、有責配偶者(不貞・暴力など夫婦関係破綻の原因を作った側)からの離婚請求は原則認められませんでした(最判昭27・2・19)。
しかし最高裁は大きく考え方を転換し、
一定の要件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しています。
【最高裁(昭62・9・2)による要件】
以下のすべてに該当する場合、離婚が認められ得ます。
- 長期間の別居(例:別居36年)
- 夫婦に未成熟子がいないこと
- 離婚しても相手が極めて苛酷な状態に陥らないこと(生活・精神・社会的側面)
その後の裁判例では、
・別居8年でも有責配偶者からの離婚請求を認めたもの
・未成熟子がいても事情により認められたもの
など、社会情勢を踏まえ柔軟な判断がされています。
5 最後に|離婚原因の有無・離婚が認められるかはケースごとに大きく異なります
離婚原因の判断は、判例・事実関係・婚姻生活の状況を踏まえた総合判断となり、専門的な知識が必要です。
結の杜総合法律事務所では、以下の点を丁寧にご説明します。
- 離婚原因が認められるか
- 有責配偶者からの離婚請求に応じるべきか
- 調停・訴訟へ進むべきか
- 必要な証拠や主張整理
- 弁護士費用・解決までの流れ
無理な勧誘は一切ありません。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「遺言執行者とはどのようなことをするの?|選任が必要なケースと手続を徹底解説」
1 はじめに
「遺言書があるのに遺言執行者の指定がない。相続人は遺言執行者を選任しなければならないのか?」
「家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、どんな手続や書類が必要なのか?」
遺言・相続のご相談では、このような質問を多く頂きます。
この記事では、遺言執行者が必要となるケース、選任手続、就任後の具体的な業務内容まで専門家が分かりやすく解説します。
2 遺言執行者はいつ必要?|選任の要否を分かりやすく解説
遺言書の内容は大きく次の3つに分かれ、内容によって「遺言執行者が必須かどうか」が異なります。
① 遺言執行者だけが執行できる事項(必ず選任が必要)
- 推定相続人の廃除(民893)
- 推定相続人の廃除の取消し(民894②)
- 認知(民781②)
これらは遺言執行者がいなければ法的に効力を実現できない内容のため、遺言執行者の選任が不可欠です。
② 遺言執行者・相続人どちらでも執行できる事項(トラブル防止のため選任が望ましい)
- 遺贈(民964)
- 一般財団法人の設立(一般法人152②)
- 信託の設定(信託3二)
- 生命保険金受取人の変更
相続人間で意見が分かれたり、協力を得にくい場合は、遺言執行者を選任することで手続がスムーズになり、争いの予防につながります。
③ 遺言執行が不要な事項(選任不要)
- 相続分の指定(民902)
- 遺産分割方法の指定(民908)
- 遺産分割の禁止(民908)
- 遺言執行者の指定(民1006①)
- 遺言の撤回 など
上記のように、内容により遺言執行者の必要性は異なります。
遺言の種類・構成を正しく判定することが重要であり、専門家に確認するメリットの大きいポイントです。
3 遺言執行者を家庭裁判所で選任する手続|必要書類・期間の目安
遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が就任できない事情がある場合には、家庭裁判所で選任手続を行います(民1010)。
■ 選任申立てができる人(利害関係人)
- 相続人
- 受遺者
- 遺言者の債権者
- 相続財産管理人
- 相続財産清算人 など
■ 管轄の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(家事209①)。
■ 必要書類(標準的なもの)
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)
- 遺言書(写しまたは検認調書謄本)
- 遺言執行者候補者の住民票等
- 利害関係を証する資料(戸籍等)
※遺言書が検認済の場合、家庭裁判所に記録が残っていれば一部省略が可能。
■ どんな場合に裁判所は選任する?
- 遺言内容に「遺言執行者必須事項」が含まれる
- 相続人間の対立があり、遺言の内容が実現できない
- 相続人の協力が得られない
- 相続財産が多岐にわたり管理が複雑
遺贈が絡む案件や相続人が複数いるケースでは、家庭裁判所での選任は非常に一般的です。
4 遺言執行者の具体的な業務内容(時系列で理解)
遺言執行者は、遺言内容を実現するために幅広い権限と義務を持ちます(民1012)。
(1)遺言書の検認手続(必要な場合)
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」を行います(民1004)。
検認前に開封してしまうと過料の対象となるため注意が必要です。
※公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要。
(2)遺言書の正本・謄本の取得(公正証書遺言の場合)
相続手続で必要となるため、公証役場で請求して取得します。
(3)遺言書情報証明書の取得(自筆証書遺言・法務局保管)
(4)遺言の有効性の確認(方式・遺言能力・内容)
方式違背や遺言能力の欠如が疑われる場合、無効確認訴訟が検討されます。
(5)相続人・受遺者の調査・通知(民1007)
出生から死亡までの戸籍を取り寄せて相続人を確定し、遺言内容を通知します。
受遺者に対しては遺贈の受諾の意思確認も必要です。
(6)財産目録の作成・交付(民1011)
不動産・預貯金・株式・保険等を調査し、相続財産を目録にまとめ相続人へ交付。
(7)遺言の実現(執行)
- 不動産の名義変更
- 銀行口座の払い戻し
- 遺贈財産の引渡し
- 廃除手続 等
遺言執行者は「善良な管理者の注意義務」を負いながら業務を行います。
(8)遺言執行終了の通知
執行が完了したら相続人等に終了を通知します(民1020)。
(9)報酬・費用の精算
遺言に記載がある場合はその通り。
ない場合は相続人との協議、合意できなければ家庭裁判所が決定します。
5 まとめ|遺言執行者の選任は専門家に相談することで安心・確実に進められます
遺言執行者は、
- 遺言書の確認
- 相続人の調査
- 名義変更
- 遺贈手続
- 財産管理
など、法律知識と実務経験が必要な場面が多く、専門性の高い業務です。
特に、
- 相続人間の対立がある
- 不動産・預貯金・株式等の財産が複雑
- 遺贈がある
- 廃除や認知など法律行為を含む
といったケースでは、専門家が遺言執行者になることでスムーズに手続が進みます。
6 当事務所が選ばれる理由|弁護士×税理士によるワンストップ相続サービス
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、
弁護士・税理士である代表髙橋が、法律と相続税の両面からサポートいたします。
- 相続・遺言・遺産分割に強い弁護士が対応
- 税理士法人を併設(東北地方で唯一の運営形態)
- 相続税申告までワンストップ対応
- 事前に費用・手続の流れを丁寧に説明
- 強引な勧誘なし・安心して相談できる体制
遺言執行だけでなく、遺産分割・相続税申告・財産調査まで一括対応が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「非正規労働者(有期契約社員)を契約期間満了前に解雇することはできるのか?」
1 はじめに
物価高騰や景気悪化などにより、人件費の見直しを迫られる企業も増えています。その中で、有期契約の従業員(契約社員・パート・アルバイト等の非正規労働者)を契約期間途中で解雇できるのかというご相談が多く寄せられています。
しかし、有期契約労働者の契約期間中の解雇は、法律上強い制限があり、正社員よりもはるかに厳しい基準で判断される点に注意が必要です。
本コラムでは、企業が知っておくべきポイントを、裁判例も交えながらわかりやすく解説します。
2 有期労働者の「契約期間途中の解雇」は原則認められない
『有期労働契約の途中で労働者を解雇するには、“やむを得ない事由”が必要です。これを欠く解雇は無効となる可能性があります。』
期間の定めのある労働契約(有期契約)は、双方が一定期間働くことを約束するものです。そのため、
契約期間満了前に解雇が認められるのは、極めて例外的なケースに限られます。
(労働契約法17条1項、民法628条)
これは派遣労働者の場合も同様で、派遣先の都合で派遣契約が終了しても、労働者との雇用契約を途中終了させることはできません(プレミアライン事件)。
3 契約期間途中の解雇が認められる「やむを得ない事由」とは
『無期契約(正社員)の解雇よりも厳しい基準で判断されます。』
(1)有期契約期間中の解雇
有期契約の解雇には、
「期間満了まで待てないほどの特別・重大な事情」が必要
と裁判例でされています(大阪運輸振興事件ほか)。
例としては、
- 重大な非違行為
- 重大な経営危機で事業存続が困難
など、極めて深刻なケースが該当します。
なお、途中解雇が無効となった場合でも、その後契約期間が満了した場合は、雇止めの有効性を別途判断することになります(最判令和元年11月7日)。
(2)試用期間中の有期契約労働者の解雇
試用期間中であっても、
- 「客観的合理性・社会通念上の相当性」(三菱樹脂事件)
- 有期契約の「やむを得ない事由」
の双方が必要とされます。
ただし、試用期間の趣旨を考慮して、“やむを得ない事由”の判断はやや緩やかに認められるとした裁判例(東京高判令5・4・5)もあります。
4 裁判例にみる「無効とされた例」「有効とされた例」
▼【期間途中の解雇が無効とされたケース】
- 受注減による人員整理では「やむを得ない事由」に当たらないと判断(東京高決 平21・12・21)
- 塾長の能力不足を理由とした解雇は重大事由とは言えず無効(仙台高 秋田支判 平24・1・25)
- 社員への暴力行為があったが、偶発的で悪質性が低いとして無効(東京地判 平29・5・19)
▼【期間途中の解雇が有効とされたケース】
- 公益法人で収入減が避けられず、業務内容上の事情から給与引下げが不可避と判断され、やむを得ない事由が認められた例(東京高判 平21・11・18)
▼【途中解雇が無効でも、満了時の更新拒否は別途判断される】
- 解雇が無効であっても、契約期間満了による終了について判断すべきとした裁判例(最判 令和元・11・7)
▼【試用期間中の解雇が有効とされたケース】
- 能力不足が著しく、他部署への配置転換も困難で、「やむを得ない事由」を認めた例(東京高判 令5・4・5)
5 途中解雇が有効でも、会社に過失がある場合は損害賠償が必要
『やむを得ない事由の発生について、使用者(会社)に過失があれば損害賠償責任が発生します。』
民法628条により、
- 解雇自体は有効
- しかし、会社の不注意により“やむを得ない事由”が発生した
場合、労働者に対して損害賠償責任を負うことがあります。
人件費削減を目的とした安易な途中解雇は、
解雇無効リスク・損害賠償リスクを抱えるため、慎重な判断が必要です。
6 まとめ(企業が押さえるべきポイント)
- 有期労働者の途中解雇は原則禁止
- 正社員より厳しい「やむを得ない事由」が必要
- 試用期間中でも制限は残る
- 無効とされた裁判例が多数
- 有効な場合でも会社に過失があれば損害賠償
- 雇止めの判断は別途必要
途中解雇は極めてハードルが高く、専門家の判断が不可欠です。
7 労働問題でお困りの企業様へ
結の杜総合法律事務所では、
- 従業員の解雇問題
- 有期契約の更新・雇止め
- 労働契約書の作成・見直し
- 人事・労務全般のトラブル対応
など、企業の労働問題を幅広くサポートしています。
顧問契約をご利用いただくことで、日々の労務リスクを大幅に軽減できます。
初回相談は丁寧に状況を伺い、無理な勧誘は一切行っておりません。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
コラム「自己破産における免責とは?手続き・影響・注意点を仙台の弁護士がわかりやすく解説」
あなたが借金の返済に行き詰まり、「もうどうしようもないかも…」と不安を抱えているなら、最終的な手段として検討されるのが「自己破産」です。その中でも、手続き上の山場となるのが 「免責」 の許可です。
本コラムでは、個人(自然人)が自己破産を申し立てた際に、裁判所が免責を許可したときにどのような影響があるのか、どんな場合に免責されない可能性があるのか、さらに手続きの流れや弁護士相談のポイントまで、仙台・宮城で実務を扱う弁護士の視点からわかりやすく解説いたします。
目次
- 免責とは何か?
- 免責を受けるとどうなるか
- 債務の免責
- 保証人・担保物権の影響
- 非免責債権とは
- 免責申立ての手続き/復権
- 免責されない(不許可)ケースとは?
- 主な免責不許可事由(11項目)
- 裁量免責とは
- 仙台・宮城で弁護士に相談すべき理由
- 料金・流れ・安心できる理由
- よくある誤解・Q&A
- まとめ・まずはお気軽にご相談を
1.免責とは何か?
自然人が自己破産を申し立てると、最終的に裁判所が「免責」を許可するかどうかを判断します。免責とは、破産者の債務(支払義務)を法的に免除する制度です。
この「免責」が許可されることで、借金問題から再スタートを切るための重要な鍵となります。
2.免責を受けるとどうなるか
(1)債務の免責
- 破産手続開始決定が確定し、かつ免責許可決定が確定した場合、破産者は 破産債権者に対する債務 について責任を免れます(破産法第253条①)。
- 破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前に生じた請求権で、財団債権に該当しないものを指します(破2⑤)。
- 免責許可決定前に支払を約束していても、その責任を免れます。また、免責後に再度支払い約束をしても無効とされる場合が多いです。
(2)保証人・担保物権の影響
主債務者が免責を受けても、 保証人の債務 や 担保物権の実行 には影響を及ぼしません(破253条②)。
つまり、借金を保証していた方・抵当権などが付いていた場合、その請求・実行は別途残ることがあります。読者の皆様にはこの点をきちんと理解して頂くことが重要です。
(3)非免責債権とは
免責しても支払義務が残る債権があります。例として、税金・悪意の不法行為に基づく損害賠償請求・養育費・罰金などが挙げられます(破253①ただし書)。
(4)免責申立ての手続き/復権
- 債務者が破産手続開始の申立てをしたとき、原則として同時に免責許可申立てを行ったものとみなされます(破248④)。
- 免責許可決定が確定した後、破産者は復権(破255条)し、破産による 資格制限 が解除されます。つまり、一定の職業制限・役職制限などから解放され、社会復帰のスタート地点となります。
3.免責されない(不許可)ケースとは?
(1)主な免責不許可事由
破産法は、免責不許可となる具体的な事由を11項目定めています(破252①)。 主なものは以下の通りです。
- 債権者を害する目的での財産隠匿・損壊・債務の仮装など(破252①一)
- 著しく不利益な条件での債務負担・信用取引による不利益処分(破252①二)
- 義務なき担保の供与・債務消滅行為(破252①三)
- 浪費・賭博・その他射幸行為による著しい財産減少・過大債務(破252①四)
- 例えば、度を超えた遊興・高価品購入、仮想通貨の過大投機等が問題となる可能性があります。
- 信用取引における詐術/債務原因となる事実を知りながら取得(破252①五)
- 帳簿隠滅・偽造(破252①六)
- 虚偽の債権者名簿提出(破252①七)
- 裁判所の調査で説明拒絶・虚偽説明(破252①八)
- 破産管財人の職務妨害(破252①九)
- 免責許可決定から7年以内に再申立て等の事由(破252①十)
- 破産法上の義務(説明義務・協力義務等)違反(破252①十一)
(2)裁量免責
上記に該当するとしても、裁判所が「免責許可が相当」と認める事情があれば、免責を許可する 裁量免責 の制度があります(破252②)。 実務上も、免責不許可事由に該当していても、かなりの割合で免責許可が認められているのが現状です。
4.仙台・宮城で弁護士に相談すべき理由
当事務所「結の杜総合法律事務所」は、仙台・宮城を拠点に 自己破産・免責・債務整理 を多数取り扱っており、地元ならではの安心感ときめ細やかなサポートを強みとしています。
以下のような点で、相談の価値があります。
- 地元対応:宮城県・仙台市での申立て実務を熟知、地方裁判所対応もスムーズ。
- 弁護士直通相談:初回無料相談/明確な料金表提示で、安心してご利用いただけます。
- 手続きの流れ・料金・リスク などを丁寧にご説明。無理な勧誘は一切無し。
- 早期再スタート支援:免責が許可された後も、信用回復・再建支援までフォローします。
借金・返済でお悩みのあなた、一人で悩まず、まずは専門家の話を聞くことが大きな一歩です。
よくある誤解・Q&A
Q1. 免責を受ければ、全ての借金がゼロになるのですか?
A. ほとんどの破産債権について支払義務を免れますが、税金・養育費・罰金等の非免責債権は免れません。
Q2. 保証人になっていたら、自分も免責されますか?
A. 主債務者の免責は保証人に影響しません。保証人としての請求・担保実行は別途生じる可能性があります。
Q3. ギャンブル・浪費した借金でも免責されますか?
A. 浪費や賭博等は免責不許可事由となる可能性がありますが、必ず免責が否定されるわけではなく、裁量判断もあるため早めに専門家へご相談下さい。
5.まとめ・まずはお気軽にご相談を
本稿では、自己破産における「免責」が何を意味するのか、許可を受けたときの効果・許可を受けられない可能性があるケース・そして仙台・宮城での弁護士相談のメリットを整理しました。
借金問題・返済不能の状況に直面したとき、早期の専門家相談がその後の人生を大きく左右します。結の杜総合法律事務所では、破産手続きの流れ・利用の適否・実際にかかる料金等を、弁護士が丁寧にご説明しております。無理な勧誘は一切しておりません。
まずは 無料相談またはお問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。お一人で悩まず、安心してお話をお聞かせください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。